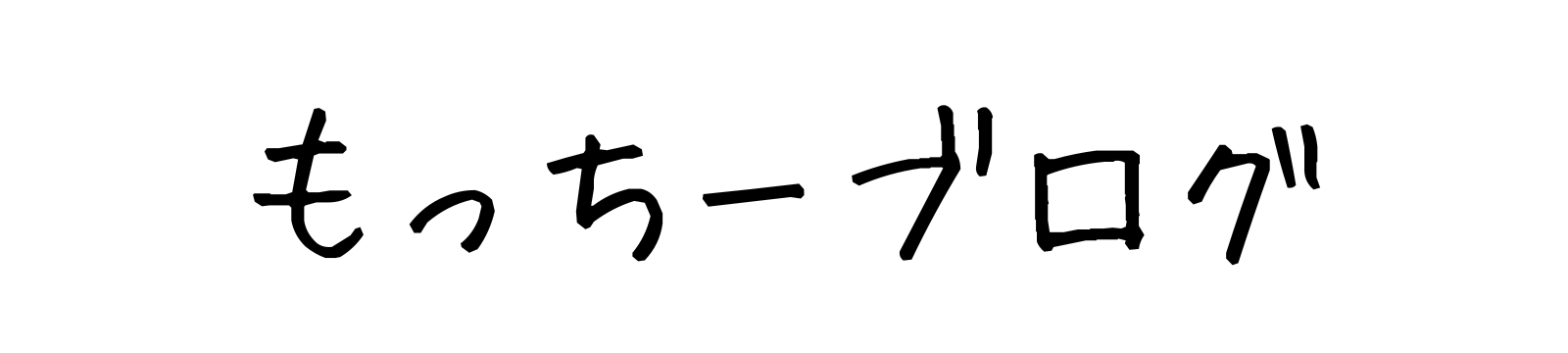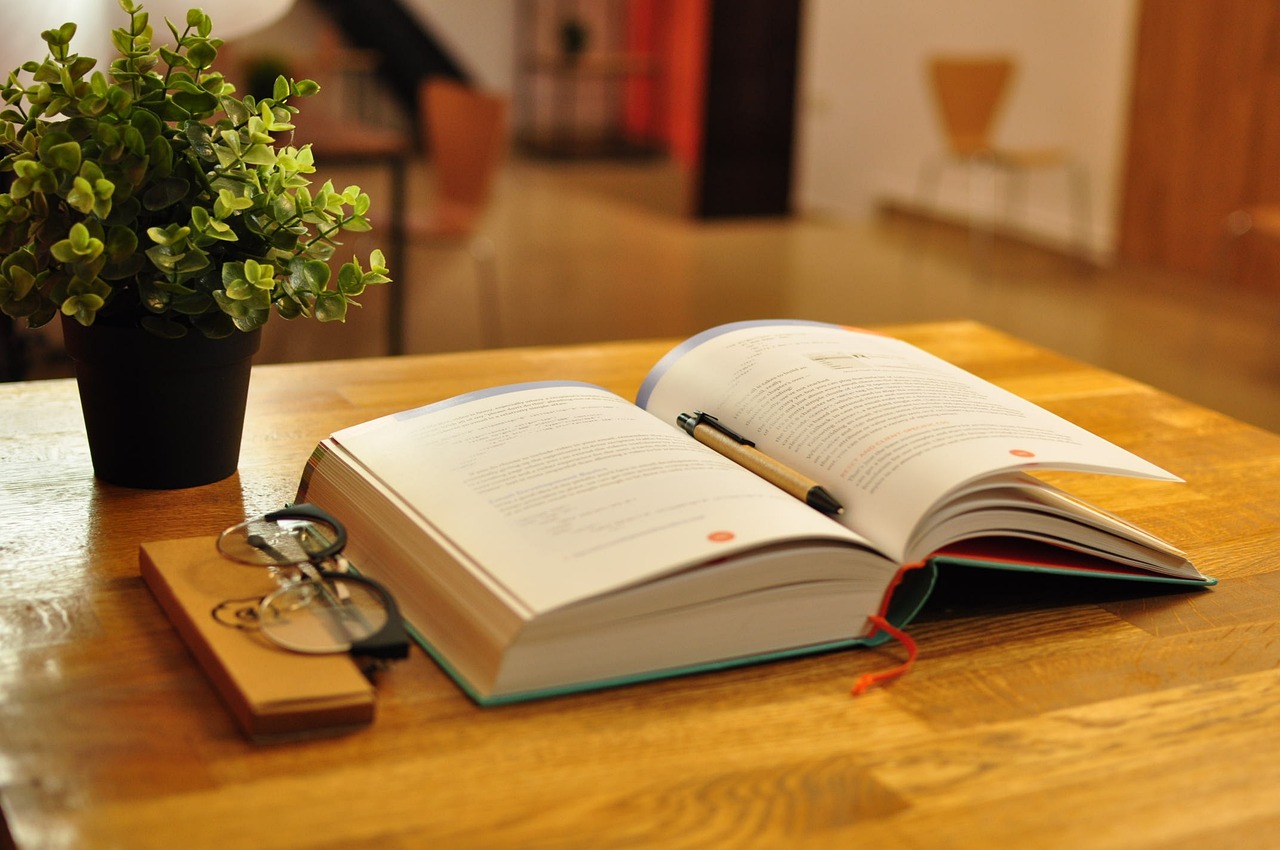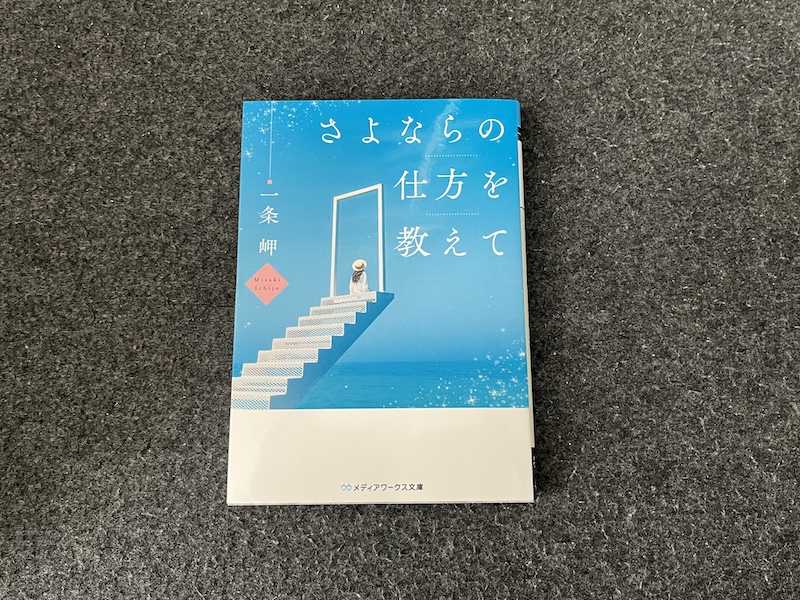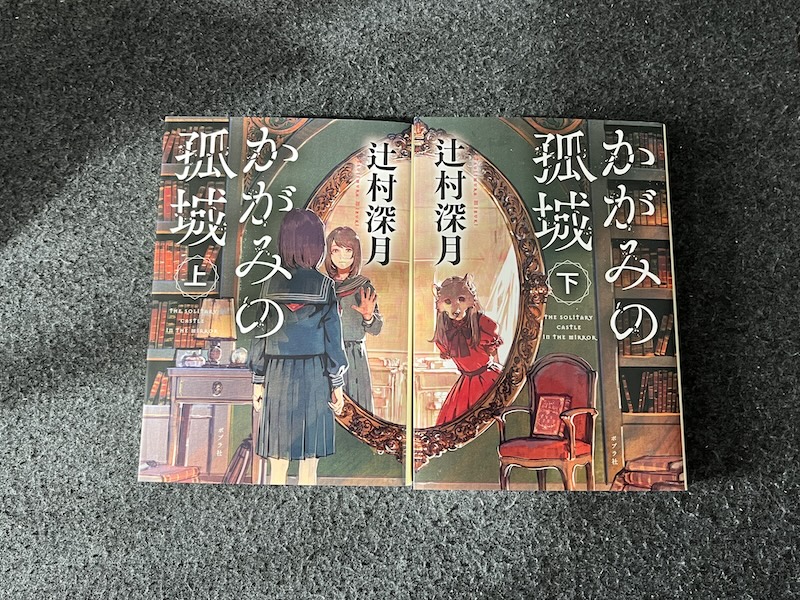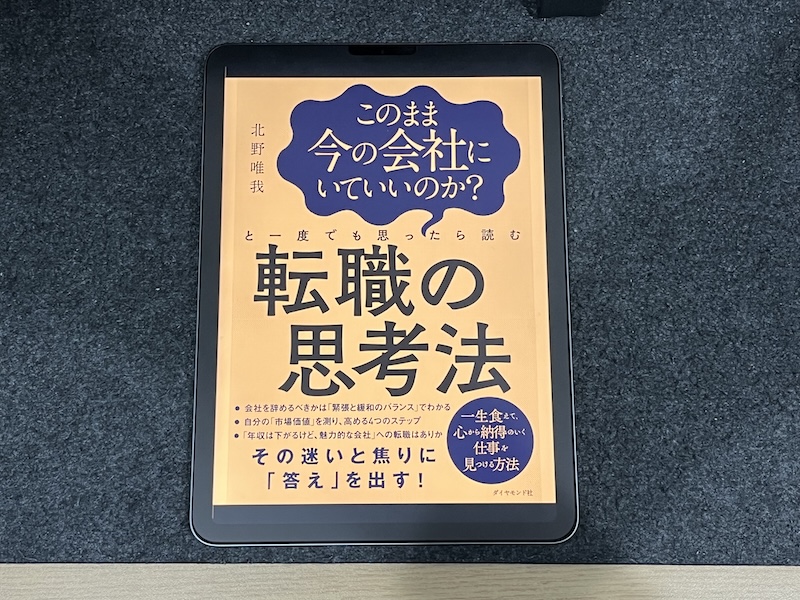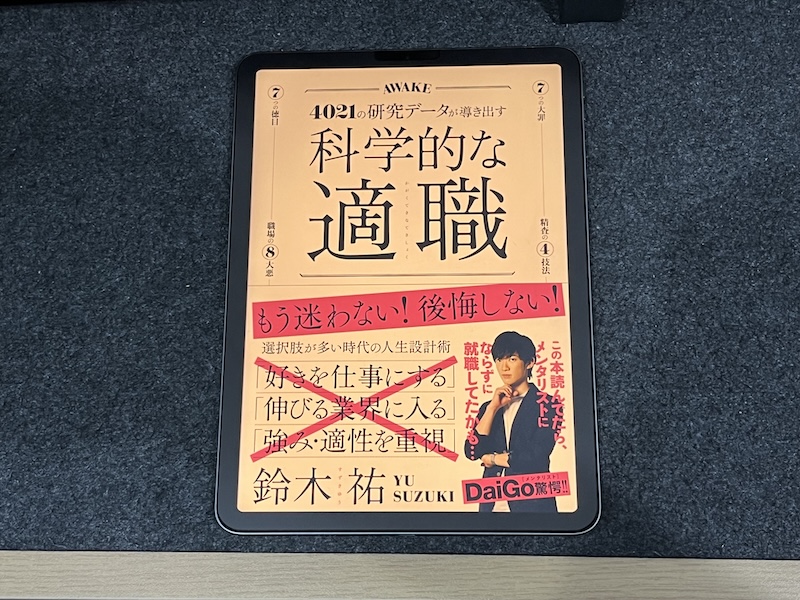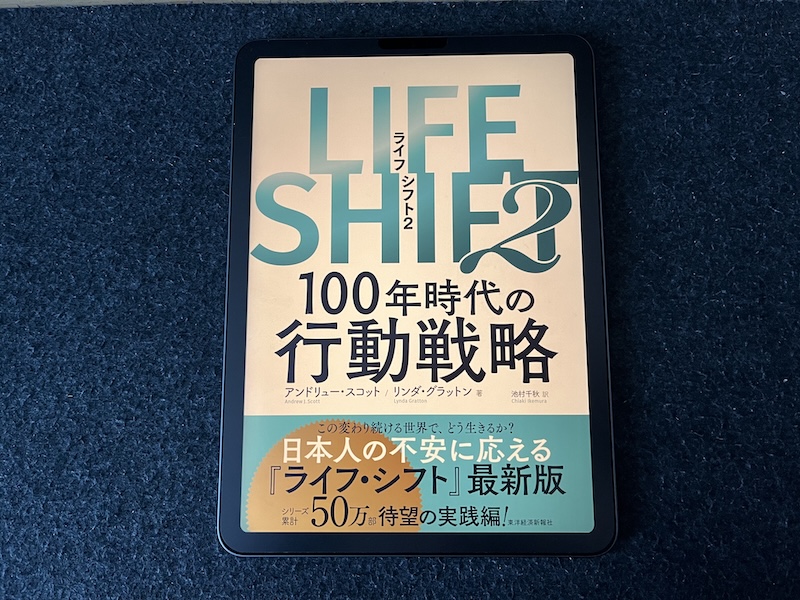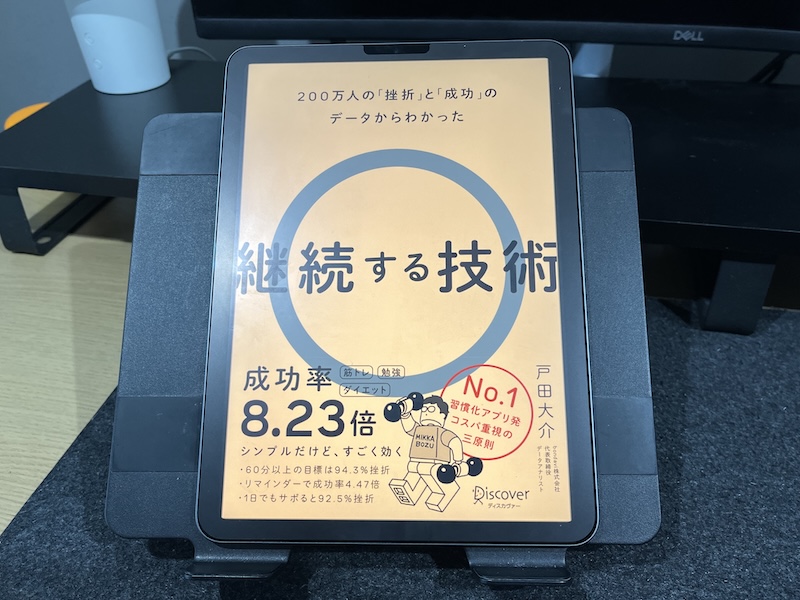こんにちは、もっちーです。
今回は「社会人が勉強を継続するためのコツ」について、自分の経験から学んだことを紹介していきます。
まず始めに
- 「疲れていて集中できない…」
- 「何から始めれば良いか分からない…」
- 「仕事が忙しくて勉強する時間がない…」
このような悩みを持っている人は多いのではないでしょうか?
自分も働きながらWebマーケティング(SEO・広告運用など)やデータ分析(統計学・Pythonなど)を学んできた経験から、社会人ならではの勉強の難しさをよく理解しています。
この記事では、実際に効果があった方法を具体的に紹介していくので、何かしらの参考になると嬉しいです。
- 社会人が勉強を継続できない理由
- 仕事と勉強を両立させるためのコツ
- 気軽に試せるオススメの勉強法について
それでは見ていきましょう!
仕事終わりの勉強が難しい3つの理由
朝起きた時に「仕事が終わったあとに勉強するぞ〜」と決めていても、なかなか実行できない経験はありませんか?
当たり前かもしれませんが、これには理由があります。
- とにかく仕事終わりは疲れが溜まりやすい
- 定時ぴったりで帰れず予定通りに勉強できない
- 急な飲み会などのイベントがあると断りづらい
これらの3つがおもな原因だと思います。
社会人として働く上では仕方がないことなので、このような状態であっても勉強できる時間を意識的に作りだすことが重要です。
ちなみに自分は飲み会だけは絶対に参加しないようにしています(忘年会も行きませんでした)

とはいえ会社によっては、なかなかイベントへの参加を断ることが難しい場合もあったり・・。
このような場合には自分なりにルールを決めることが大切だと思います。
- 飲み会は月1回だけの参加にする
- 早起きの習慣をつけて始業前に勉強する
- 残業を減らすために仕事の効率化を意識する
具体的な方法はこのあとに詳しく解説していきます。
今の働き方や生活リズムを少しずつ変えていくことで、継続的に勉強できる時間を確保できるはずです。
集中力を持続させる実践的な方法
社会人の勉強で大切なのは「限られた時間を効率的に使うこと」です。
ここでは具体的な時間管理の方法と、集中力を保つためのテクニックを紹介します。
タイマーを使った時間管理
まず気軽に試せて効果的なのが「ポモドーロ・テクニック」です。
- 25分勉強する
- 5分休憩を取る
- これを4回繰り返す
- 長めの休憩(15-30分)を入れる
この1セットで約2時間になりますが、忙しくて時間を取れない場合は(3)の繰り返しを2回にするのもOKです。
このサイクルを繰り返すことで、集中力を途切れさせることなく勉強を続けられます。
私も実践していますが、実際にやってみて気づいたメリットは
- 集中力が続く
- 達成感が得られる
- 休憩時間が楽しみになる
などのモチベーションが下がることなく勉強できるようになった気がします。
スマホのタイマーでも良いですが、「Be Focused」などの専用アプリを使うと便利です。
 もっちー
もっちー無料でも問題なく使えて、有料プランでも240円なのでコスパが高いです
進捗を記録して可視化する
勉強の記録をつけることで、自分の成長を実感できます。
- 勉強時間
- 理解できた内容
- 次に勉強する予定
などなど・・何をやったか思い出せるように意識してメモすることがおすすめです。
もし可能であれば、メモに残した結果をグラフで可視化できると継続するモチベーションが上がります。


自分はエンジニアとして個人開発を始めたので、その作業を継続するためにGitHubというサービスで継続状態を可視化できるようにしました。
何日か継続できていることが分かると、「今日もやらなくては・・!」といった気持ちになります。



強迫観念かもしれませんが、継続するきっかけを作れるので良いと思います
まずはスマホのメモ帳だったり、ふせんや紙のノートでも構いません。
大切なのは継続できる方法を選ぶことです。
飽きない工夫をする
同じ勉強方法を続けていると、どこかのタイミングで飽きてしまう可能性があります。
そのような時は少しだけいつもの方法に変化を加えてみることがオススメです。
- 朝:音声教材を聴く
- 昼休み:スマホで動画を見る
- 夜:教科書で復習する
みたいな感じで英語の勉強をしていたことがありました。
このように時間帯によって学習方法を変えることで、途中で飽きることなく長く続けることができます。


締め切りを意識する
「余裕ができたら始めよう」と思っていると、ほとんどの場合で永遠に始まりません(笑)
これを防ぐためには締め切りを決めることが大切です。
- 3ヶ月後に模試を受ける
- 半年後に資格試験にチャレンジ
- 来月までに○○の章を終わらせる
適度なプレッシャーがあることで、勉強のペースを落とさずにメリハリつけて続けることができます。
仕事の合間で勉強する具体的な方法
とはいえ「仕事終わりは疲れていて勉強なんて出来ない・・」と考えている人は多いのではないでしょうか?
そこで夜以外の時間で自由に使える時間を用意して、限られた時間のなかで効率的に勉強することがオススメです。
- 早朝
- 通勤中
- 昼休み
それぞれ詳しく見ていきましょう。
早朝
起きたばかりの朝は脳がいちばんリフレッシュしている時間帯なので、この時間を活用しない手はありません。
朝型にするメリット
- 頭が冴えていて集中できる
- 誰にも邪魔されない
- 達成感を感じられる
- 1日を有意義にスタートできる
具体的な時間の作り方
- いつもより30分早く起きる
- すぐに顔を洗って目を覚ます
- コーヒーなどを飲んで準備する
- そこまで重くない勉強を始める
「朝早く起きるのは無理…」という人も、たとえば30分だけでも早く起きてみるのをオススメします。
少しずつ起きる時間をずらしていくことで、気付いたら余裕で早起きできるようになっていると思います。
通勤時間
片道30分の通勤時間なら、往復で1時間も勉強する時間を作ることができます。
とはいえノートに書いたりする勉強は難しいので、狭い範囲でも大丈夫な勉強が良いと思います。
- Kindle本を読む
- 単語帳アプリで暗記
- 音声のコンテンツを聴く
- ビジネス系のYouTubeを観る
個人的にオススメなのは「音声のコンテンツを聴く」ことです。
PCに向かう時間の多い仕事だと目が疲れますし、体を動かす仕事だと体力的な消耗がありますよね。
音声コンテンツであれば耳だけで勉強できるので、仕事に向けた体力を温存しておくことができます。


お昼休み
昼休みを食事だけで終わらせるのはもったいないと思います。
- 10分で食事を済ます
- 15分くらい仮眠を取る
- 残り20分で本を読んだりする
ポイントは「毎日の同じ時間に同じことをする」だと思います。
勉強の習慣をつけておくことで、スキマ時間を見つけたら自然と勉強モードに入れるようになるはずです。